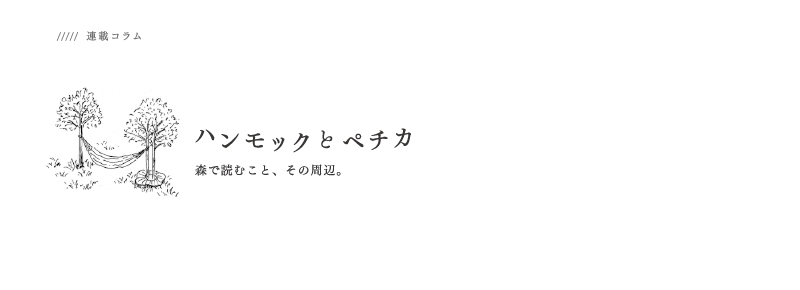[time & place] 真冬のある日、薪ストーブの前で
[book] 『長い冬』ローラ・インガルス・ワイルダー著(岩波少年文庫)
今日も雪がひらひら舞い始めたかと思い、次に窓に目を向けたら、視界一面まっしろけになっていた。
細かい雪が上から横から降りなぐり、山も林も畑も見分けがつかない。
時折、山の方向から吹いてくる強い風が家をガタガタっと揺らしていくほかは、風の止み間にギィギィと鳴く鳥の声だけが聞こえる。
白一色の光景をしばらくぼうっと見つめ続けていると、時間の感覚も、今いる場所さえうやむやになるような、起きているのに眠っているみたいな状態になって、薪ストーブの薪が「ごとん」と崩れる音で、はっと我に帰る。
よく冗談で「冬は冬眠しています」と言うけれど、この場所で冬を重ねるうちに、あながち冗談でもないと思い始めている。
「朝日に輝く白銀の草原」や、「粉砂糖をまぶしたお菓子のような森」...といったロマンチックさだけじゃなく、ちっぽけな人間が歯向かうことなどとてもできない、凶暴で容赦のない、本来の「雪」の姿を知ることができたのも、関東ではもっとも日本海側の気候に近く、寒さは北海道並みの、この村に暮らすようになってからのこと。
読みかけの本のなかでも、嵐が吹き荒れている。
こちらの吹雪は、北軽井沢とは較べものにならない。
7ヶ月もの間、三日三晩荒れ狂い、束の間の太陽に気を緩めたとたん、雲行きは急転、またゴーゴーピューピューと猛り狂う。
暖炉にくべる薪や石炭は底をつき、干し草を編んで代用にする。
町に荷を届ける貨物列車が雪で動けなくなったから、食料も乏しくなり、パンを焼くためにはなけなしの小麦をコーヒーミルで挽いたものを使うしかない。
いつ終るともしれない嵐のなかで、ひもじさに耐え、干し草を編み、ミルを廻し続ける日々(これらは一刻も手を休められない)。
だんだんと意識がぼんやりし、お腹も減らず、お話や歌も耳に入らなくなってくる。
吹雪は、冬は、永遠に終わらないかもしれない……
「大草原の小さな家」で知られるローラ・インガルス・ワイルダーの物語。
そのうちの一編、「長い冬」。
手元の岩波少年文庫版でも、上・下巻、2冊にわたる。
タイトルどおり、ほんとうに長い、長い、これでもかというような冬。読んでいるだけで胸がつまって苦しくなってきてしまう。
秋口に見つけたジャコウネズミの巣(いつもよりとっても分厚い)が示したとおり、ふらりと現れたインディアンが予言したとおり、その年の冬は猛吹雪とともに10月から4月まで続いた。
かれら開拓者たちに与えられた草原地帯には、実際に7年に一度、こんな冬がやってきたという。
100年も前のアメリカの開拓民・インガルス一家の暮らしを、晩年になって娘ローラが描いた一連の「大草原」シリーズは、わたしが出会った初めての長編の「物語」だったかもしれない。
いつも強くて頼りになってヴァイオリンの上手な「父ちゃん」。
しっかりものでユーモアもあって優しい「母ちゃん」。
目の見えないメリーにローラ、キャリー、グレースの4姉妹。
テレビドラマ版も大好きで、土曜日の夕方6時、かぶりつくように観ていた。
「これぞアメリカ西部!」と思えるような壮大なオープニングテーマは今でも朗々と口ずさめるし、草原を転がりながら駆け下りて来るエプロン姿のローラたちの画もはっきり憶えている。(映像とは怖いもので、いいのか悪いのか、私のなかでの「父ちゃん」の姿は、あのもじゃもじゃ頭に胸毛も勇ましいマイケル・ランドンが定着してしまった。)
そして幼い私のなかで、大草原のイメージと、北軽井沢の風景は、いつしか重なり合う。
実際に、別荘地を抜けた先の手付かずの草地を「大草原」と名付けて、自分はローラになったつもりで、花を摘み、駆け回った。
現実の「父ちゃん」は、オオカミを銃で撃ったり、ヴァイオリンを弾けたりはしなかったが、肩車をして森のあちこちを巡ったり、満点の星空を見に夜に連れ出してくれたりした。
あのころ家族で過ごした時間と「大草原シリーズ」に出会わなかったら、今この村での暮らしに巡りつくことはなかったとも思う。
(その村はずれに、大草原シリーズの訳者・恩地三保子さんの山荘があったのも、偶然と言えば不思議な偶然。)
その重なり合うイメージには、もうひとつ重要な共通点があった。
カイタクチ。
当時の私は知る由もないが、ローラになりきってはしゃいでいた北軽井沢の「大草原」も、第二次大戦後、この地に入植してきた人々の手で拓かれた、たしかな「開拓地」だったのだ。
今、私たちが北軽井沢と呼んでいる土地の大部分は、戦中を開拓団として満州で過ごし、その後引き揚げと同時に再び入植者として不毛な火山灰土に立ち向かった人たちの歴史の上にある。(ということを、私は移住後にはじめて知った。)
夏場、農家のお手伝いでお世話になっているSさんも、そのまわりの農家さんたちも、その開拓世代の子や孫にあたる。
雄大な山並みに囲まれた青々とした畑や、牛がのんびり草をはむのどかな光景は、何百年も前から当たり前にここにあったような気がしていたけれど、実はまだ60年そこそこの、それも裸の人の手が生み出したものだったと知って、足元がグラグラゆれるような思いになる。
入植の人たちの暮らしぶりは相当厳しいものだった、と何かの走り書きで読んだ。
うすっぺらなバラックにくたびれた身を寄せ合い、どんなふうに過ごしていたのだろう。
冬、こんな吹雪の日にはどうやって暖をとり、春までを凌いできたのだろう。
ローラたちは、辛い夜にはヴァイオリンの音に合わせて歌をうたい、物語を聴き、神様に祈った。
この村の人には、どんな歌が、物語が、祈りがあったのだろう…。
そのとき、ローラは気がついた。ローラは、寝床の上にとび起きた。そして大きな声でよびかけた。
「父ちゃん!父ちゃん!ロッキーおろしが吹いているよ。」
「父ちゃんもきいてるよ、ローラ。」父ちゃんはつぎの部屋から答えた。「春がきたんだよ、さあ、またおやすみ。」
春を告げる、吹雪のときとはまた別の風が吹いて、ローラたちの長い冬が終わる。
読みながら、ついつい強ばっていた読者の肩の力も、ここで、ふぅ、とほどける。
長い冬の間にはいろいろあった。
いつもたくましい「父ちゃん」が元気をなくしかけたことも、「母ちゃん」が取り乱してしまったことも、村の中には自分たちだけ助かろうと小麦を隠しこんだ人たちもいたし、雑貨屋の主人は若者が命がけで手に入れてきた小麦に暴利をつけて売りさばこうとした。
それはそうだ。冬の厳しさ(加えて餓え)は、人間の弱いところをぐりぐりとえぐるものだから。
でも、嵐に対してはなすすべのない人間たちも、生きるためには、図太く、たくましかった。
私の大好きな「母ちゃん」のセリフ。
きちんと熟しきれていない青いかぼちゃを使ってパイを焼こうとする場面。
「青いカボチャのパイ?母ちゃん、あたしそんなパイって聞いたことないよ。」(ローラ)
「母ちゃんもよ。でもね、人が聞いたことのあることばかりしていたら、たいしたことは何もできっこないよ。」
この逞しさ。頑丈さ。
冬の厳しさは、人間の本当の強さや知恵や賢さも、思い出させてくれる。
(今の時代の私たちにそれがどれだけ残っているかは別として…。)
(現実の、この本を読んだあとでは吹雪とも呼べない程度の)窓の外の雪嵐はいつしかやんで、青空といっしょに浅間山の輪郭が姿を見せた。
真っ白なマントにくるまって、優雅に、矍鑠と、たっている。夏よりも、うんと近くに、大きく見える。
60年前の人たちも、晴れた日のあの山を眺めては、しばらく寒さを忘れては見とれたに違いない。
ローラや、姉妹たちや、アルマンゾみたいな元気な子どもたちの雪遊びの声が、裸の雑木林に響いていたのに違いない。
この長い冬の間に、この土地に埋もれつつある「物語」についても、調べてみたくなった。